目次
「インドの経済は日本を越える」。Japan Timesによると、そんな声が世界から聞こえてきているようです。国際通貨基金 (International Monetary Fund)は、その変革は早くも今年2025年に起こると予想しています。
| インド | 日本 | ソース | |
|---|---|---|---|
| GDP成長率 | 6.5% | 1.1% | International Monetary Fund 2025 |
| 人口 | 14.4億 | 1.2億 | United Nations 2024 |
| 労働人口 | 5.96億 | 0.69億 | The world fact book 2023 |
| GDP/1人当たり | $2,500 | $34,000 | International Monetary Fund 2025 |

ムンバイの実情から予測する2025年ビジネスチャンス
南アフリカからの飛行機が到着したのは、ムンバイ。インド経済の金融の中心地であるムンバイは世界で12番目に裕福な都市です。インドの富裕層が住む都市でもあり、百万長者は4万6000人、100人近くの大富豪が住んでいます。そのムンバイのローカルバス、電車に乗り、街を歩いて、こんな実情を見てきました。
ムンバイの実情➀ 交通インフラの目覚ましい発展
現在1日700万人の乗客を運ぶMaha Mumbai Metroですが、最初のBlue Lineが開通したのは2014年、僅か10年前です。現在運行中の4つの路線に加えて8つの路線が2026年までに完成予定。現在許可申請中の路線を加えると、合計17路線、53駅となる計画です。Maha Mumbai Metroの他に、空港と都市をつなぐNavi Mumbai Metro (2023年開通、1路線運行中、3路線建設中)、やMumbai Monorail (2014年開通、2029年までに8路線開通予定)もあり、交通インフラの改善が期待されます。


また、インフラ設備の欠如、車両人口の増加、過度の交通渋滞といった問題を解決するため高速道路や高架の建設も進んでいます。「Mumbai Urban Infrastructure Project」はWorld Bankの資金提供を受けて2003年から取り組まれている都市開発です。
交通インフラのデリー発展に加えて、デリーとムンバイを結ぶ物資専用の電車路線もあり、物資の流通がより円滑になっています。安全で効率的なロジスティクスが可能になったことで新たなビジネスが生まれてきそうです。





Google Mapでもバスや電車を使った移動ル―ト検索をすることができます。バス停の場所や到着時間なども正確に網羅されており、公共交通機関を利用しての移動をスムーズにすることができました。昔はいつ来るか分からない電車を何時間も駅で待っていたものですが、現在はアプリで時刻を検索、席を予約することもできるようになり、交通インフラの改善は目覚ましいと感じました。

ムンバイの実情② 食文化の多様化
駅界隈にひしめくレストランの大多数はインド料理レストランで、その3割くらいが肉料理を提供しないVeg Restaurantを謳っています。Chineseの文字を掲げるレストランも、1割~2割ほどあったようです。
路上の屋台で中国風のフライドライス、フライドヌードルも見られました。インドとは思えない醤油の香ばしい匂いは行列ができるほどの大人気で、鉄でできた平たい大きなフライパンに作られた炒飯は1時間もしないうちに空になっていました。
偶然見つけたセブン・イレブンではチキンハンバーガー、唐揚げ、サンドイッチを発見しました。ハンバーガーは160円、唐揚げは100円、チキンサンドイッチは260円でした。インドではお酒の販売に規制がかかっている地域もありますが、ムンバイではセブン・イレブンでビールやワインを販売していました。販売されているお酒は、どれもインド産のものでした。








牛や豚を食べる文化のないインドですが、鳥の料理は多くあるようです。魚の捕れる南部では魚料理も盛んです。「舌のグローバル化」と「異国文化への興味」の進化が見られたことから、チキンカツや焼き鳥、お好み焼きなど、日本のストリートフードが受け入れられるのではないかと感じました。





20年前のインドでは、レストランのメニューでカレー以外を見た記憶がありません。ムンバイのホテルではビュッフェ式の料理などもありましたが、日本食や中華料理はもちろん、スパゲティやハンバーガーのような洋食は見つかりませんでした。洋食を求めてマクドナルドに行くものの、ジャガイモのバーガーとマサラチキンのバーガー、ポテトにもマサラがかかっていたのを覚えています。今は、マクドナルドに加えてバーガーキングもあり、ベーカリーやコーヒーショップもありました。

ムンバイの実情➂ 女性ファッションの近代化
インド全体の伝統衣装であるサリー、パンジャブ地方で着られるパンジャブ・スーツ。女性はこのどちらかを身にまとっているのは大都市のムンバイでも例外ではありませんでしたが、現在は半分以上の人がジーンズやスカートなどの洋服を纏っています。
中にはクロップ・トップにヒップハングジーンズを着る女性も。そういったトレンドの服装は「90年代アメカジ」を思わせます。ヘアスタイルは、長い髪を一本に結うのが年齢を問わず一般的でしたが、現在はベリーショートやボブの女性も見かけたことも印象的でした。
日本文化の影響を全く感じないインドですが、日本特有の「ゆるかわ」的な女性のファッションは文化的にも受け入れられやすく、インドにとって斬新なデザインなのではないかと思います。また、インドではあまり「ブランド志向」ではないように感じましたが、ユニクロやMujiなどの海外で人気の日本ブランドはどのように受け入れられるのだろう、と興味を持ちました。





では男性は?と言うと、男性のファッションは過去20年ほど変化がないようです。男性の洋服は当時もジーンズにシャツという恰好が一般的でした。巨大なマーケットではありとあらゆる服飾類が売られていますが、物価が安いことには驚かされます。日本の衣料品店で買う4分の1くらい、というイメージです。
ムンバイの実情➃ 人口の41%が住む大スラム都市
経済成長とインフラの発展に関するニュースを見ているとインドからは貧困層が消えたかのように感じますが、ムンバイの人口の41%はスラム街に住んでいます (Time of India) 。スラム街の面積をデータで比較すると、2005年には都市の8%がスラム街であったのに対し、2022年現在は7.3%に減少しています。しかしこれは改善されたのではなく、インフラ整備や都市化のためにスラム街の住民を追い出したことに起因しています。世界で三番目に大きいスラムであるDharavi地区では、2km2に100万人の家があります。
The most DENSELY POPULATED place on EARTH, 1 Million people in 2km SLUM (Youtube)
私が訪ねたByculla地区は、ビジネスの中心地にあり建設中の高層ビルやブランドストアが入ったデパートなどの近くにありました。Byculla地区がユニークなのは、スラム街でありながら服飾品などを製造する小さな工場兼、そこで働く労働者の家屋があることです。各家屋にはトイレや浴室はなく、公共のトイレと洗い場で毎回料金を支払って利用します。それらの場所を利用する人も、それを貸すことをビジネスにする人も、どうにかして少しでも良い暮らしをしようとする力強さを感じました。この生きる力の強さこそがインドという国の強さではないかと思います。
インドでビジネスを発展させるのであれば、この膨大な人口を締めるスラム街の人々の暮らしが便利になるサービス、衛生環境が改善されるアイデアを売ることを検討してみるのはいかがでしょうか。














まとめ
インドを訪ねたことで、経済ニュースではわからない実情を見ることができました。目覚ましい発展に驚くこともあれば、日本では見たことのないような貧困、衛生環境も未だに大きな社会問題であるという事実を感じられました。一人で旅行をした所感としては、インフラも改善され、安全リスクも大幅に軽減したと感じましたので、インドでビジネスを展開したいという方は、是非一度足を運んで何層にも分かれているインド人の生活を実体験されることをお勧めいたします。
・The Little Book of Indian Business by Fynshots
ムンバイの空港で見つけました。現在のインドのことが分かりやすく多岐に渡って書いてあります。今回の記事の情報のヒントとしても活用できました。
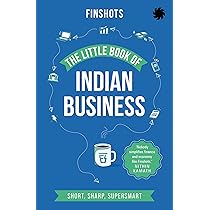
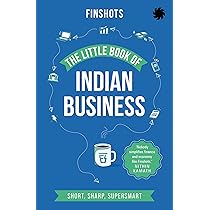
・Sadique Taxi Service and Tour +91 98670 31700
Byculla地区をよく知るタクシードライバーの彼が工場の中まで案内してくれて、ムンバイの実情を教えてくれました。


多言語コミュニケーションにお悩みでしたら、プロの通訳に任せるのも一つの手段です。
企業への依頼やコミュニケーションシーンなど、特に正確性が求められる場合は、機械翻訳に頼らずプロの通訳・翻訳会社に依頼しましょう。
OCiETeではオンライン通訳や現地通訳サービスで、言語コミュニケーション課題をサポートいたします。
現地のアテンドや商談時の通訳、会社案内や契約書の翻訳、さらに即戦力人材のご紹介や海外進出に向けた事前リサーチや営業代行も承ります。
コーディネーターが、業界や商品・サービスごとに精通した担当者をシーンや用途に合わせ、ご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。

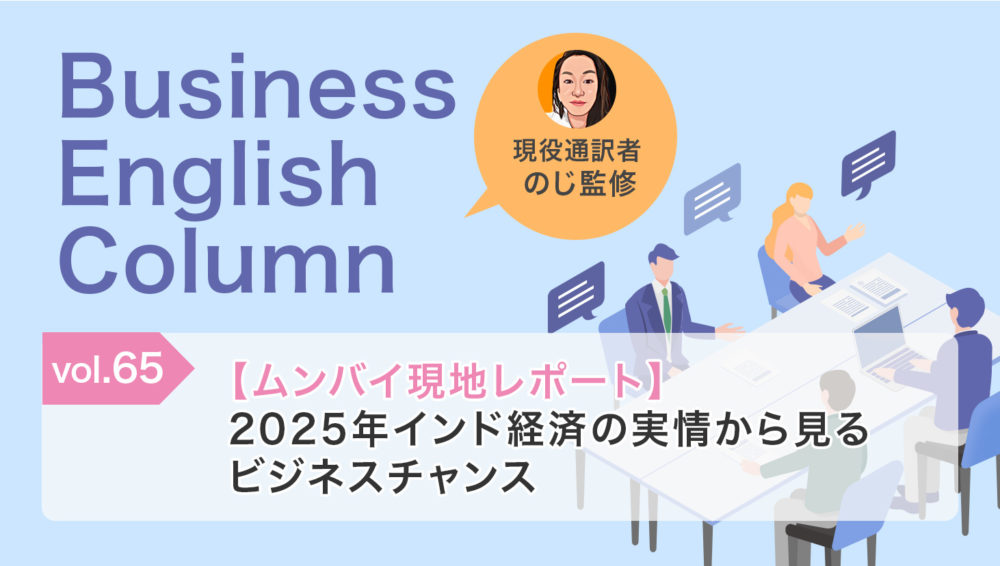
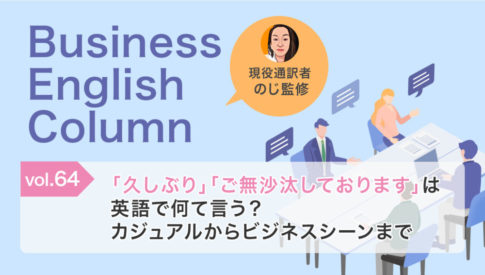

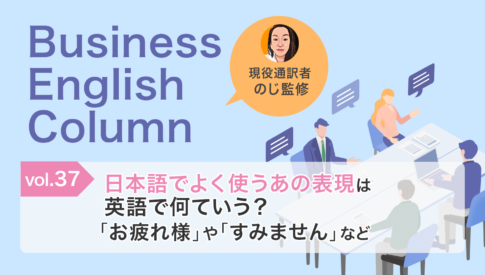

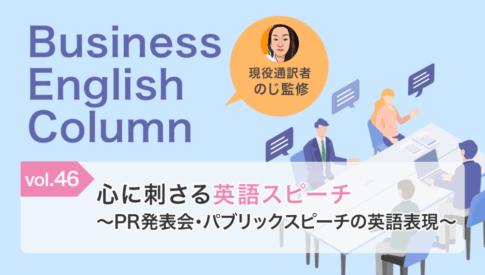
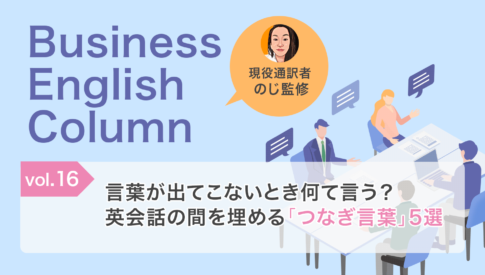
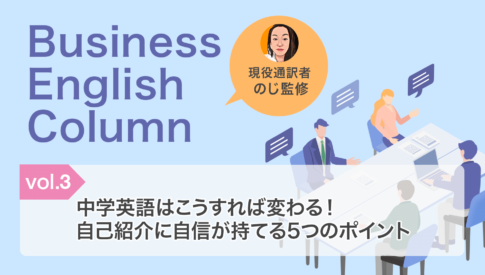
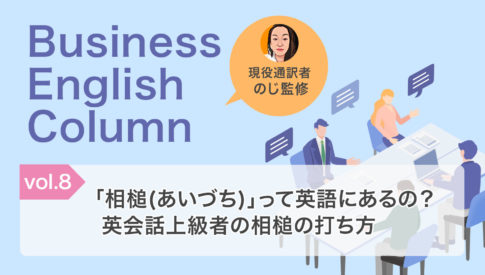
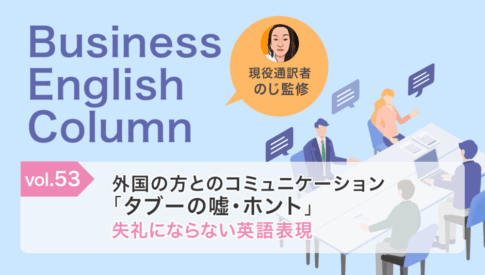


筆者が前にインドに行ったのは20年前でした。その頃と比べて変わったこと、ムンバイで数日を過ごして感じたビジネスチャンスについて、個人的な視点からまとめました。